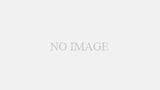— ひばり (@emihibari) November 3, 2019
自分も強度近視で、網膜剥離一歩手前で手術した。近視矯正技術は、現代の技術水準では全然進んでいない。
いったいどうしたら良いものか。記事にあるような予防でも限度がある。
— sorata31@財務省から国民を守る党 (@sorata311) November 3, 2019
青森の田舎で育って強度近視になった自分はどうすれば良いんだ… https://t.co/o1Rkor06Go
— まろちゃん (@Kazumaro531) November 3, 2019
強度近視、NHKニュースで話題に!坪田一男教授とは
坪田 一男(つぼた かずお)
慶應義塾大学医学部眼科教授、日本抗加齢医学会理事長をされています。
略歴 ☆1971年 – 慶應義塾普通部卒業 ☆1974年 – 慶應義塾高等学校卒業 ☆1980年 – 慶應義塾大学医学部卒業、医師免許取得、米国ECFMG合格、慶應義塾大学医学部眼科学教室入局(主任:植村恭夫教授) ☆1983年 – 国立栃木病院(現国立病院機構栃木病院)眼科医長 ☆1985年 – 厚生省臨床研修指導医留学生としてハーバード大学留学 ☆1985年 – 米国マサチューセッツ州医師免許取得 ☆1987年 – ハーバード大学角膜クリニカルフェローシップ卒業、帰国後再び国立栃木病院眼科医長 ☆1988年 – 厚生省修練指導医認定 ☆1989年 – 慶應義塾大学より医学博士授与、日本眼科学会専門医認定 ☆1990年 – 東京歯科大学眼科助教授 慶應義塾大学眼科講師(現在まで) ☆1992年 – 東京医科歯科大学難治疾患研究所非常勤講師(1996年9月まで) ☆1993年 – 旭川医科大学医学部非常勤講師(現在まで) ☆1995年 – ハーバード大学訪問教授(Invited by Prof.Wayne Streilein) ☆1998年 – 東京歯科大学眼科教授、東京歯科大学市川総合病院眼科部長、メルボルン大学訪問教授 (Invited by Prof.Huh Taylor)
☆2004年 – 慶應義塾大学医学部眼科教授、東京歯科大学眼科客員教授
受賞歴 ☆1988年4月 – 日本眼科医会学術奨励賞 ☆1991年4月 – 興和財団研究助成賞 ☆1992年4月 – 上原研究財団研究奨励賞 ☆1993年9月 – Honor Award、American Academy of Ophthalmology ☆1998年12月 – 慶應義塾大学医学研究奨励事業:坂口基金奨励研究賞
☆2000年11月 – The first Claes Dohlman Award、Tear Film and Ocular Surface Society
–健康