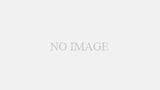PVAを混ぜるだけで
製造しやすく実用性が高いとのこと。
今後期待できますね♪#液体のり #ガン細胞治療 #白血病治療 pic.twitter.com/cTthZGxd1x
— 田舎もんやす君(投資家) (@toaruuthuujinn) January 22, 2020
雨、冷え込みを感じない朝です。今朝のニュース、文房具用品の液体のりががんの放射線治療に有効とか!うれしい発見ですね。 pic.twitter.com/qEmURWEl6A
— いっちゃん (@ichicodokidoki) January 22, 2020
がん治療効果が向上、液体のり成分を活用 東工大など / https://t.co/GOeEjyG0ir #日経 #ドコモ #au #ソフトバンク #ワイモバイル #UQ #リアルメディア #モバイル pic.twitter.com/iNHG3k3eNU
— 株式会社リアルメディア (@realmediajp) January 22, 2020
ええ、「液体のり」でがん細胞ほぼ消失😱😱😱
がん細胞に薬剤を取り込ませておき、中性子をあててがん細胞を壊す放射線治療で、薬剤に液体のりの主成分を混ぜると治療効果が大幅に高まることを東京工業大のチームが発見し、23日発表した。 pic.twitter.com/HpZH3A4Ine
— 🌈sero🌱 (@g4Bpl1AsevtGpr7) January 22, 2020
5月30日、白血病の治療に大きな効果が表れる可能性のある研究成果が発表されました。
山崎聡特任准教授によると白血病治療に大切な細胞を大量に培養することにマウスで成功した事を確認したとの事です。
コンビニの液体のりでも培養できる事も確認出来たようです。
市販「液体のり」、白血病治療の救世主に? 専門家驚嘆https://t.co/fhSXZNRrYU
白血球や赤血球に変われる造血幹細胞は、0.5リットルで数万円するような培養液でも増やすことが難しかった。ところが、洗濯のりや液体のりの主成分で培養したところ、幹細胞を数百倍にできたという。 #医療 pic.twitter.com/Ajc5PasAFS
— 朝日新聞デジタル編集部 (@asahicom) May 30, 2019
山崎聡特任准教授の発表内容
・名前 山崎 聡 / YAMAZAKI Satoshi ・学位 博士(生命科学) ・職名 特任准教授 ・所属 医科学研究所 所属サイトURL
・専門分野 血液内科学 ・研究テーマ 成体外における造血幹細胞の効率的な増殖方法の確立 ・研究テーマに関するキーワード 骨髄ニッチ,造血幹細胞,体外増幅 ・実績等URL
液体のりで造血幹細胞の増幅に成功 〜細胞治療のコスト削減や次世代幹細胞治療に期待〜
1. 発表者 山崎 聡(東京大学医科学研究所 幹細胞生物学分野 特任准教授)
2. 発表のポイント ◆通常の培養で使用する高価なウシ血清成分やアルブミンの代わりに液体のりの主成分であるポ リビニルアルコール(PVA)を用いることで、安価に細胞老化を抑制した造血幹細胞の増幅が 可能になった。 ◆マウス造血幹細胞を用いた実験により、1個の造血幹細胞を得ることができれば複数の個体へ 造血幹細胞移植が可能であることがわかった。 ◆本発見は、ヒト造血幹細胞にも応用可能であると期待され、おもに小児の血液疾患に対して移
植処置の合併症リスクを軽減した安全な造血幹細胞移植が提供できるとともに、幹細胞治療や 再生医療への応用や医療コストの軽減に期待される。
3. 発表概要 東京大学医科学研究所の山崎 聡 特任准教授(幹細胞生物学分野)を中心とした研究チーム(ス タンフォード大学と理化学研究所との共同研究チーム)は、マウスの造血幹細胞(注 1)を用い た研究から、細胞培養でウシ血清成分や精製アルブミン(注 2)さらには組み換えアルブミンが 造血幹細胞の安定的な未分化性を阻害していることを突き止めました。しかし、アルブミンのよ うなタンパク質を培養液に加えないと、造血幹細胞の細胞分裂が誘導できないことが問題でした。 今回、本研究チームは“液体のり”の主成分であるポリビニルアルコール(PVA)(注 3)という 化学物質が血清成分やアルブミンの代わりになり、しかも血清成分やアルブミンと異なり造血幹 細胞の未分化性を維持したまま数ヶ月培養可能であることを明らかにしました。1ヶ月間以上も
造血幹細胞を未分化な状態で増幅培養できる報告は世界で初めてであり、本技術により、ドナー から1個の造血幹細胞さえ分離採取できれば、複数の患者が治療できる可能性が示されました。
4. 発表内容 (研究の背景) 造血幹細胞は、全血液細胞を一生涯にわたり供給することができる組織幹細胞です。この造血 幹細胞は、血液疾患を根治する際の骨髄移植(造血幹細胞移植)には欠かせない細胞であり、ド ナーからの供給が非常に重要です。しかし、高齢化社会によるドナーの減少により、骨髄バンク
や臍帯血バンクの補助的なシステムの構築が課題となっております。そこで本研究チームは、白 血病を含む血液/免疫疾患患者へ応用を目指して造血幹細胞を生体外で増やす技術開発を進めて いました。
山崎聡特任准教授の現在の研究過程
今回の研究成果と関連がある研究計画の紹介と思われます。
骨髄組織における細胞ダイバーシティーの理解と制御
研究代表者 山崎 聡
東京大学医科学研究所 幹細胞治療部門
本研究は骨髄内に存在する細胞ダイバーシティーを理解することによる人工骨髄の構築を目的としている。
私は10年以上、造血幹細胞を中心とした骨髄環境の研究をしてきた。
これまでの研究によって骨髄に存在する造血幹細胞の状態を詳細に明らかにし、造血幹細胞の細胞周期を制御している細胞として骨髄内に存在する非髄鞘シュワン細胞であることを同定した。
近年では骨髄内における特異的なアミノ酸濃度環境が存在することを明らかにすることで造血幹細胞や骨髄内に存在する細胞の制御を可能にした。
さらには骨髄組織を透明化することでマスウの全骨髄構造を3次元イメージング技術によりデータの取得を行い骨髄環境と造血幹細胞の局在関係を明らかにしている。
これら各研究の結果とその理解は、人工骨髄の構築という最終的な研究者のゴールがある。
その理由として、人工骨髄システムを用いることで造血幹細胞から全ての血液細胞を分化誘導が可能であり、造血幹細胞を維持できる予想から新たな造血幹細胞バンクの基盤を創造できると考えていることである。
また骨髄には間葉系幹細胞や他に様々な未熟な未分化細胞が存在することから移植細胞のソースとして応用可能であると考えられ、さらには人工骨髄を透明の容器にいれた蟻の巣のような観察システムを構築することで正常細胞や白血病細胞の動態を詳細に解析できる。
以上のことから本研究課題は細胞社会ダイバーシティーの統合的解明と制御からの人工骨髄の作出を目指す。
山崎聡特任准教授のこれから
東京大の山崎聡特任准教授のチームが、英科学誌ネイチャーに発表したはまだ、マウスの実験の段階です。
ただ、人の細胞にも応用できる方法とみられており、白血病の治療が格段と進歩する可能性を秘めています。
わずかでも造血幹細胞があれば増殖し移植が可能となりさらに複数の患者に適用できる事になります。
これからの研究でさらに進化していき実用化されることを期待しましょう。
–その他